- 2022-
- 2017-2021
- 2012-2016
- 2007-2011
- 2002-2006
- 1997-2001
- 1992-1996
- ALL
受賞者の所属・役職は受賞当時のものです。
2025

スタンフォード大学 地球システム科学科
ロバート・B・ジャクソン教授
森林・草原・湿原などの陸域生態系の炭素循環の専門家で、土壌・植生・土壌細菌群集の関係に関する先駆的な研究を行ってきた。また、化石燃料の使用や自然の生態系から発生する二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素などの温室効果ガスの収支を定量化している。2017年からは、グローバルカーボンプロジェクト(GCP)の議長として温室効果ガス排出量の監視と削減を主導している。
※ものがたりは後日掲載予定です。
2025

ハイランド・リワイルディング社創設者・CEO
カーボン・トラッカー・イニシアティブ初代会長
ジェレミー・レゲット博士
Carbon Tracker Initiative (CTI)の初代会長として「カーボンバブル」の概念を提唱し、化石燃料資産の経済リスクを明らかにした。CTIの活動を通じて投資家や政策立案者に影響を与え、ダイベストメント(投資撤退)運動を促進した。また、経済活動と環境保全の両立を目指す実践的な活動として、英国を代表する太陽光発電企業を創業。最近ではスコットランドで自然回復と地域社会の繁栄を結び付ける取り組みを推進している。
※ものがたりは後日掲載予定です。
2024

ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン、グローバル・プロスペリティ研究所
ロバート・コスタンザ教授
自然の価値
自然環境が人間に提供する生態系サービスの経済的価値が、当時の世界のGDP総額を上回っていることを初めて示すなど、それまで過小評価されていた生態系サービスの重要性を世界に示した。
2024

生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム (IPBES)
自然が人間にもたらすもの
生物多様性、生態系サービス、そして自然が人間にもたらすものに関する最新の知見と科学を提供し、政策決定や具体的な行動の促進に貢献した。
2023

プリマス大学教授、プリマス大学海洋研究所所長
リチャード・トンプソン教授
エクセター大学教授、エクセター大学生態毒性学研究グループ長
タマラ・ギャロウェイ教授
プリマス海洋研究所 海洋生態学・生物多様性 科学部門長
ペネロープ・リンデキュー教授
海の中の小さな脅威
海洋中にマイクロプラスチックを発見し、動物プランクトンを含む海洋生物がそれらを摂取していることを明らかにしたことなどにより、この問題を国際社会に知らしめた。
2023

ルーヴァン・カトリック大学教授
災害疫学研究センター所長
ジョンズ・ホプキンス大学ブルームバーグ公衆衛生大学院 人道的健康センター上級研究員
デバラティ・グハ=サピール教授
過去の災害を未来の防災へ
世界の大規模災害に関する初のデータベース「EM-DAT (Emergency Events Database)」を作成し、世界各国の防災・減災に貢献した。
2022

ジグミ・シンゲ・ワンチュク第4代ブータン王国国王陛下
国の要は国民の幸福
人々の幸福を国の開発計画の中心におく国民総幸福量(Gross National Happiness: GNH)という考え方を提唱した。
2022

ウィスコンシン大学陸水学センター名誉所長 名誉教授
スティーブン・カーペンター教授
湖をめぐる生態系
湖のレジリエンス(回復力)に関する研究を行い、社会生態系に新たな視点をもたらした。地球化学的な観点から、土地利用によるリンの環境汚染に警鐘を鳴らした。
2021

カリフォルニア大学サンディエゴ校スクリプス海洋研究所 教授
気候持続可能性 エドワード A フリーマン寄附講座
ヴィーラバドラン・ラマナサン教授
CO2以外の地球温暖化をもたらすもの
短寿命気候汚染物質(SLCP)が地球温暖化に及ぼす影響を発見し、SLCP削減が、大気汚染の改善と短中期的な温暖化緩和の両方に有効であることを示した。
2021

ムナシンゲ開発研究所 創設者・所長
モハン・ムナシンゲ教授
経済・環境・社会を調和させる
開発問題を経済、環境、社会の三つの観点からとらえるサステノミクスの考え方を基に、環境経済学、政策、持続可能な開発などの研究と実践活動を行なった。
2020

ミネソタ大学 教授 大学理事、カリフォルニア大学サンタバーバラ校 卓越教授
デイビッド・ティルマン教授
健康によい食べ物は環境にもよい
農業と食習慣が健康と環境に与える影響を調べて人間の健康によい食べ物は地球環境にもよいことを突き止め、健康にも環境にもよい農業の実践と食習慣への移行を提唱してきた。
2020

シンクロニシティ・アース戦略的保全部長、元 IUCN 種の保存委員会議長
サイモン・スチュアート博士
野生生物保全の仕組みづくりと実践
絶滅のおそれのある野生生物のリスト「レッドリスト」の科学的な信頼性を高めることに貢献し、両生類の絶滅の危機に警鐘を鳴らすなど、野生生物保全のため尽力してきた。
2019

ルーヴァン・カトリック大学教授、スタンフォード大学教授・学部長
エリック・ランバン教授
全世界の土地利用状況の変化について衛星リモートセンシング技術と独自の手法によって解析し、生態系への影響や人間の経済活動との関係を明らかにして、世界規模での森林保護や持続可能な土地利用の促進に貢献した。
2019

カリフォルニア大学ロサンゼルス校地理学部教授、歴史家、作家
ジャレド・ダイアモンド教授
『銃・病原菌・鉄』、『文明崩壊』、『昨日までの世界』の三部作を通じて、人類文明史において地球環境問題がいかに重要な位置づけにあるかを独創的な視点で解き明かし、人類が目指すべき次の文明のあり方を示した。
2018

オーストラリア連邦科学産業研究機構(CSIRO)名誉フェロー
ブライアン・ウォーカー教授
変化に対応できる能力「レジリエンス」
自然が持つ「レジリエンス(何か変化が起きてもその変化に対応できる能力)」について研究し、予測不可能な変化にさらされる自然生態系と人間社会が持続するためにはレジリエンスを高める必要があると提唱してきた。
2018

国際応用水文学教授、ストックホルムレジリエンスセンター上級研究員
マリン・ファルケンマーク教授
水は地球をめぐる血流
長年にわたる水の研究を通して途上国の貧困に水問題が深く関係していることに気づき、水不足の度合いを示す指標の開発、目に見えない水「グリーンウォーター」の活用の提唱など、水問題の解決に向けて尽力してきた。
2017
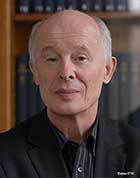
気候科学者(ポツダム気候影響研究所(PIK)創設者・所長)
ハンス・J・シェルンフーバー教授
取返しのつかないことが起きる前に
「地球システム」の解析によって地球温暖化によって将来起こりえる重大な脅威を予測し、科学的根拠をもって地球温暖化対策の必要性を国際社会に訴え続け、パリ協定の2℃目標合意に大きく貢献した。
2017

生物学者(スタンフォード大学生物学部環境科学科ビング教授)
グレッチェン ・C・デイリー教授
私たちの身近にある自然
自然保護と人間社会の繁栄の両立を目指し、人間の生活圏にある自然に着目した「カントリーサイド生物地理学」を築くとともに、自然の価値評価を政策や経済活動に組み込むため精力的に活動してきた。
2016

環境経済学者(国連環境計画(UNEP)親善大使)
パバン・シュクデフ氏
自然は「タダ」じゃない!
自然の価値を値段などで表すことでその重要性を理解できるようにする「環境会計」の普及に力を注ぎ、国の政策や企業の経済活動に環境会計を導入して持続可能な自然利用を実現する具体的な方法を提案してきた。
2016

動物学者(グラスゴー大学名誉教授)
マルクス・ボルナー教授
アフリカ、動物たち、そして人間たち
アフリカ・タンザニアのセレンゲティ国立公園において長年、野生動物と生態系の保全に携わり、地元の人たちにも活動に関わってもらうなど、自然と人間の双方を見据えて幅広い取り組みを実施してきた。
2015

経済学者(ケンブリッジ大学名誉教授)
パーサ・ダスグプタ教授
本当の「豊かさ」ってなんだろう?
人間の豊かさ、幸せのために自然環境がいかに重要かを経済学において明らかにし、自然環境の悪化と貧困の相関関係を見出した。持続可能な発展を評価するため、国の豊かさをはかる新しい基準「包括的な富の指標」をしめし、世界に影響をあたえた。
2015

経済学者(コロンビア大学 地球研究所所長)
ジェフリー・D・サックス教授
貧困はなくせる!
「臨床経済学」という独自の手法によって、各国で貧困をなくすために貢献した。地球規模の問題を解決し、持続可能で公平な世界を実現するための具体的な方法を世界に提言した。
2014
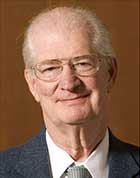
メリーランド大学公共政策学部名誉教授
ハーマン・デイリー教授
経済成長は人を幸せにできるのか
経済学に、自然、地域社会、生活の質、倫理などの要素を組込むことにより持続可能な社会の土台となる考え方を生み出した
2014
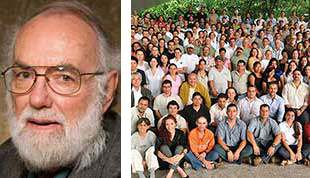
ダニエル・H・ジャンゼン教授
ペンシルベニア大学生物学科教授
コスタリカ生物多様性研究所(INBio)
持続可能な開発の施策や政策提言等を通じ、世界の先進国・途上国の何れもが学ぶべき価値あるロールモデルを提供した
2013

海洋研究開発機構地球環境変動領域特任上席研究員
松野太郎博士
気象科学の研究・予測・解明に優れた指導力を発揮、地球温暖化と気候変動について世界の認識を深める大きな貢献をした
2013

カリフォルニア大学デービス校教授
ダニエル・スパーリング教授
交通が環境に及ぼす影響について、科学・技術から行政までを含む包括的な実践研究により、都市の環境施策に大きな進歩・指針をもたらした
2012

ブリティッシュ・コロンビア大学教授、FRSC(カナダ王立協会フェロー)
ウィリアム・E・リース教授

グローバル・フットプリント・ネットワーク代表
マティス・ワケナゲル博士
人間がどれだけ自然環境に依存しているかを表した指標“エコロジカルフットプリント”を提唱し、過剰消費のリスクの見直しに大きく貢献した
2012

ジョージ・メイソン大学環境科学・政策専攻教授
トーマス・E・ラブジョイ博士
人間の活動が生物多様性を損ね、地球環境の危機に至ることを学問的に初めて明らかにするとともに、世界の環境保全に大きな影響を与えた
2011

米国商務省次官、米国海洋大気局(NOAA)局長
ジェーン・ルブチェンコ博士
生物多様性を起点とした海洋生態学の開拓に大きく寄与し、また科学者の社会的責任の重要性を明瞭に世に示した
2011

ベアフット・カレッジ
伝統的知識を重視した教育活動により途上国の農村地域住民を支援し、自立的な地域社会構築の模範を造り上げた
2010
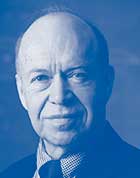
NASAゴダード宇宙科学研究所ディレクター、コロンビア大学地球環境科学科客員教授
ジェームス・ハンセン博士
“放射強制力”の概念を基に“将来の地球温暖化”を予見し、その対策を求めて米国議会等で証言した。気候変動による破壊的な損害を警告し、政府や人々に早急な対応が必要であることを説いた
2010

英国 環境・食糧・農村地域省(DEFRA)チーフアドバイザー、イーストアングリア大学 ティンダールセンター 環境科学議長
ロバート・ワトソン博士
NASA、IPCCなど世界的機関において科学と政策を結びつける重要な役割を果たし、成層圏オゾン減少や地球温暖化等の環境問題に対し世界各国政府の具体的対策推進を導く大きな貢献をした
2009

日本学士院会員、東京大学名誉教授
宇沢弘文教授
地球温暖化などの環境問題に対処する理論的な枠組みとして社会的共通資本の概念を早くから提唱し、先駆的でオリジナルな業績を上げた
2009

ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス 教授
ニコラス・スターン卿
最新の科学や経済学を駆使した気候変動の経済的・社会的な影響・対策を「気候変動の経済学」として報告し、明確な温暖化対策ポリシーの提供により世界的に大きな影響を与えた
2008

フランス国立科学研究センター名誉主任研究員、フランス科学アカデミー会員
クロード・ロリウス博士
極地氷床コア分析に基づく気候変動の解明、特に、氷期、間氷期間の気候変動と大気中の二酸化炭素との相関関係を見出し、現在の二酸化炭素の濃度が過去にない高いレベルにあることを指摘し、地球温暖化に警鐘を鳴らした
2008
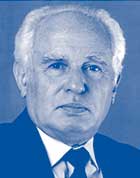
サンパウロ大学電気工学・エネルギー研究所教授、サンパウロ大学元学長
ジョゼ・ゴールデンベルク教授
エネルギーの保全・利用の効率化に関わる政策の立案施行に大きく貢献し、途上国の持続可能な発展のための先駆的概念を提唱するとともに、リオ地球サミットに向け強いリーダーシップを発揮した
2007

カリフォルニア大学(バークレー校)教授
ジョセフ・L・サックス教授
環境保護に「公共信託財産」の考え方を取り入れた世界最初の市民環境法の起草に携わり、環境保全に関わる法律を理論的に構築し、国際的にも環境法の体系確立に先駆的に貢献した
2007

ロッキー・マウンテン研究所理事長兼Chief Scientist
エイモリ・B・ロビンス博士
「ソフト・エネルギー・パス」の概念の提唱や「ハイパーカー」の発明により、エネルギー利用の効率化を追及し、地球環境保護に向けた世界のエネルギー戦略牽引に大きく貢献した
2006

国際生態学センター研究所長
宮脇 昭博士
「潜在自然植生」の概念に基づく森林回復・再生の理論を提唱・実践し、防災・環境保全林、熱帯雨林の再生に成功して、地球の緑を回復する手法の確立に貢献した
2006
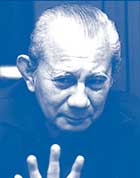
インドネシア大学経済学部・大学院教授、元インドネシア人口・環境大臣
エミル・サリム博士
持続可能な開発の概念の創設に関わり、長年国連関連会議で全地球的環境政策の推進に主導的な役割を果たし、ヨハネスブルグサミットの成功に向け大きく貢献した
2005

ケンブリッジ大学地球科学科名誉教授、ゴッドウィン第四紀研究所前所長
ニコラス・シャックルトン教授
氷河期-間氷期の気候変動の周期、二酸化炭素の関わりとそれを引き起こす地球軌道の変化を明らかにし、古気候学に貢献、将来の気候変動予測に大きく寄与した
2005

W.オルトン・ジョーンズ細胞科学センター名誉所長、A&G製薬取締役会長/マンザナール・プロジェクト代表
ゴードン・ヒサシ・サトウ博士
エリトリアで斬新なマングローブ植林技術を開発し、最貧地域における持続可能な地域社会の構築の可能性を示し、先駆的な貢献をした
2004

米国海洋大気庁 高層大気研究所 上級研究員
スーザン・ソロモン博士
南極のオゾンホールの生成機構を世界で初めて明らかにし、オゾン層の保護に大きく貢献した
2004

「環境と開発に関する世界委員会」委員長、元ノルウェー首相/WHO名誉事務局長
グロ・ハルレム・ブルントラント博士
環境保全と経済成長の両立を目指す画期的な概念「持続可能な開発」を提唱し世界へ広めた
2003

生態系研究所理事長兼所長
ジーン・E・ライケンズ博士
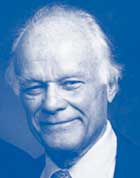
エール大学名誉教授
F・ハーバート・ボーマン博士
小流域全体の水や化学成分を長期間測定して、生態系を総合的に解析する世界のモデルとなる新手法を確立した
2003

ベトナム国家大学ハノイ校、自然資源管理・環境研究センター教授
ヴォー・クイー博士
戦争により破壊された森林を調査して、その修復および保全に尽力し、環境保護法の制定や生物種の保護にも貢献した
2002

スタンフォード大学生物学部教授
ハロルド・A・ムーニー教授
植物生理生態学を開拓して、植物生態系が環境から受ける影響を定量的に把握し、その保全に尽力してきた
2002

エール大学森林・環境学部長
J・ガスターヴ・スペス教授
地球環境問題を世界に先駆けて科学的に究明して、問題解決を国際的に重要な政治課題にまで高めた
2001
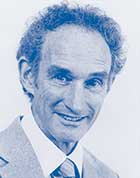
英国王立協会会長
ロバート・メイ卿
生物個体数の推移を予測する数理生物学を発展させて、生態系保全対策のための基盤を提供した
2001

オックスフォード大学グリーンカレッジ名誉客員教授
ノーマン・マイアーズ博士
生物種の大量絶滅を先駆的に警告するなど、新たな環境課題を常に提起して環境保全を重視する社会の規範を提示した
2000

世界自然保護基金(WWF)科学顧問
ティオ・コルボーン博士
「環境ホルモン」が人類や生物に及ぼす脅威を系統的な調査により明らかにし、その危険性を警告した
2000

「ナチュラル・ステップ」理事長
カールヘンリク・ロベール博士
持続可能な社会が備えるべき条件とそれを実現するための考え方の枠組みを科学的に導き、企業等の環境意識を改革した
1999
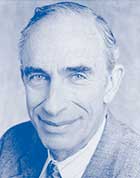
スタンフォード大学保全生物学研究センター所長
ポール・R・エーリック博士
「保全生物学」や「共進化」を発展させると共に、人口爆発に警鐘を鳴らして地球環境保全を広く提言した
1999

全人代・環境資源保護委員会委員長
曲格平(チュ・グェピン)教授
科学的な調査に基づいて環境保全の法体系を中国に確立して、広大な国土の保全に貢献した
1998

国立水文学研究所気候変化研究部長
ミファイル・I・ブディコ博士
地球気候を定量的に解析する物理気候学を確立して、二酸化炭素濃度の上昇による地球温暖化を世界に先駆けて警告した
1998

地球島研究所理事長
デイビッド・R・ブラウワー氏
環境保全の問題点を科学的に解析して、市民と連帯して多数の米国国立公園の設立に尽力、国際環境NPO活動の基盤を構築した
1997

オックスフォード大学グリーンカレッジ名誉客員教授
ジェームス・E・ラブロック博士
超高感度分析器を開発して、環境に影響する微量ガスを世界に先駆けて観測し、さらに「ガイア仮説」の提唱により人々の地球環境への関心を高めた
1997

コンサベーション・インターナショナル (CI)
地球の生物多様性を維持するため、環境を保護しながら地域住民の生活向上を図る研究とその実証を効果的に推進した
1996

コロンビア大学ラモント・ドハティ地球研究所教授
ウォーレス・S・ブロッカー博士
地球規模の海洋大循環流の発見や海洋中の二酸化炭素の挙動解析等を通して、地球気候変動の原因解明に貢献した
1996

M.S.スワミナサン研究財団
持続可能な方法による土壌の回復や品種の改良を研究してその成果を農村で実証し、「持続可能な農業と農村開発」への道を開いた
1995

ストックホルム大学名誉教授/IPCC議長
バート・ボリン博士
海洋、大気、生物圏にまたがる炭素循環に関する先駆的研究および地球温暖化の解決に向けた政策形成に対して貢献した
1995
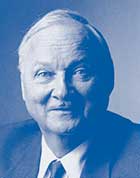
アース・カウンシル議長
モーリス・F・ストロング氏
地球環境問題解決に向け実地調査と研究に基づいた持続可能な開発の指針の確立、地球規模での環境政策に対して先駆的貢献をした
1994

キール大学名誉教授
オイゲン・サイボルト博士
海洋地質学を核としたヘドロの沈積予測、大気・海洋間の二酸化炭素の交換、地域の乾燥化予測等地球環境問題への先駆的取組みをした
1994

ワールドウォッチ研究所所長
レスター・R・ブラウン氏
地球環境問題を科学的に解析し、環境革命の必要性、自然エネルギーへの転換、食糧危機等を国際的に提言した
1993

カリフォルニア大学スクリップス海洋研究所教授
チャールズ・D・キーリング博士
長年にわたる大気中の二酸化炭素濃度の精密測定により、地球温暖化の根拠となるデータを集積・解析した
1993

国際自然保護連合(IUCN)
自然資産や生物の多様性の保全の研究とその応用を通じて国際的貢献を果たしてきた
1992

米国海洋大気庁 上級管理職
真鍋淑郎博士
数値気候モデルによる気候変動予測の先駆的研究で、温室効果ガスの役割を定量的に解明した
1992

国際環境開発研究所(IIED)
農業、エネルギー、都市計画等、広い領域における持続可能な開発の実現に向けた科学的調査研究と実証でのパイオニアワークを行った